令和6年度 愛知上組実践運動研修会を開催いたしました

令和7年3月8日午後2時より、ハーティーセンター秦荘の中ホールにて「令和6年度 愛知上組実践運動研修会」を開催いたしました。当日は多くのご門徒の皆様にご参加いただきました。
本年度の研修会では、本願寺史料研究所の上級研究員であられる岡村喜史先生を講師にお迎えし、「蓮如上人の近江における布教について」という演題でご講義をいただきました。
蓮如上人は、近江の地を中心に布教活動を展開され、十字名号を掛け軸にして本尊とする信仰の在り方を広められました。これは、より多くの人々が念仏を大切にし、阿弥陀仏を身近に感じられるような環境づくりを進めるためのものでした。
また、蓮如上人は「御文章」を用いて音声による伝道を行われました。その最初のものは、近江の金森道西という人物に宛てて書かれたとされており、カタカナ表記が用いられたのは、人々が声に出して読めるようにするためだったといいます。さらに、正信偈和讃を木版印刷によって広められ、音楽的に唱和する形を取り入れられました。これにより、全員で勤行を行い、一体感を共有することで、信仰を通じた仲間意識が育まれました。

加えて、一般の人々が自然に集まり、信仰を深められるよう、寄り合いの場を積極的に推奨されました。この流れが、「番方講」や「三浦講」の成立につながる契機となったと考えられます。
こうした布教の形は、戦国時代の社会状況とも合致し、浄土真宗は人々のつながりを強める重要な要素として広く受け入れられていきました。このように、蓮如上人の伝道の起源は近江にあり、その影響が全国へと広がっていったことが改めて明らかとなりました。
今回の研修を通じて、蓮如上人の伝道の出発点が近江にあり、その地の人々が何を求めていたのかを深く見極めながら布教を進められたことを学びました。そして、その信仰の在り方がやがて全国へと広がり、多くの人々に念仏の教えの大切さを伝えられたことを改めて感じさせていただける学びの時間となりました。
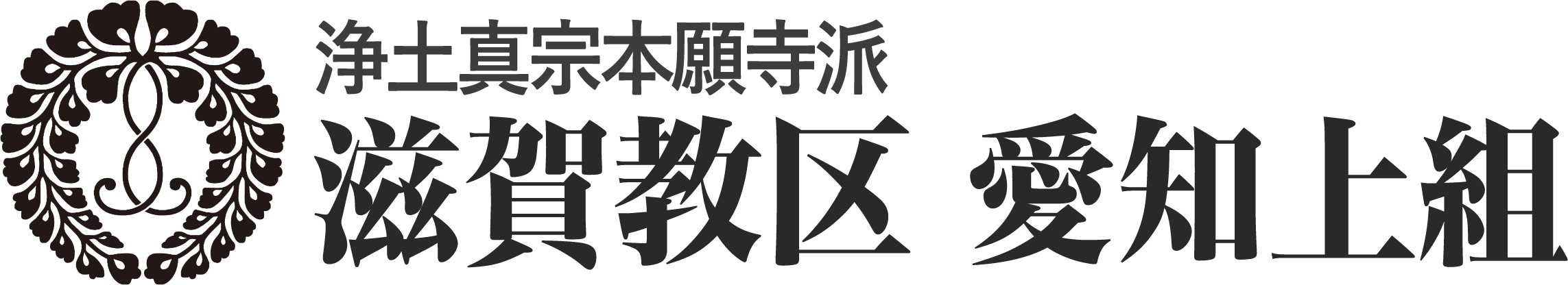



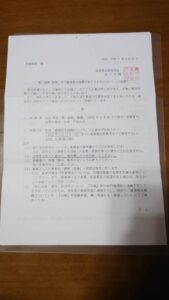


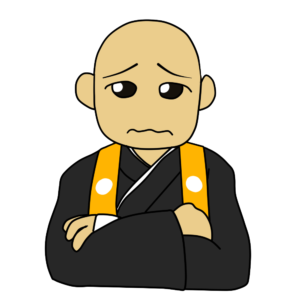


コメント